本物の”実業家 堀江貴文 行動力に満ちた天才
みんなおおきに、ペンギン先輩やで!
今日は “行動は正義” を体現する実業家、ホリエモンこと 堀江貴文氏の行動力について語るで。
良くも悪くも、迷ったら まず打席。そのスイング回数と検証速度が桁違いやねん。ほな、いこか。
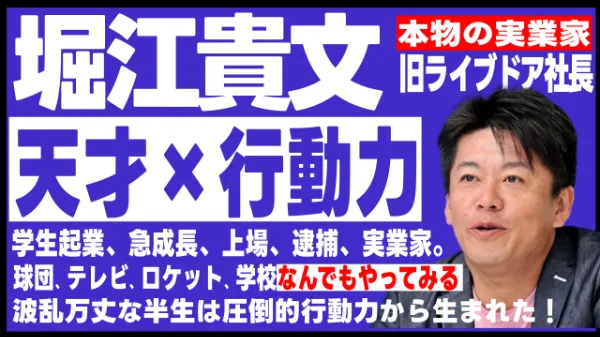
近鉄買収に即手挙げ。「無理? ほな新球団つくるわ」
2004年6月、近鉄とオリックスの合併観測で球界がざわついた瞬間、ホリエモンはその日のうちに会見を打ち、「2月から買収打診してた。正式に交渉したい」と宣言。議論の土俵に上がるんやなく、土俵そのものを先に作る動きや。これで“近鉄問題=ライブドアの選択肢”という見出しを世に定着させたんよ。
せやけど、オーナー側の空気は合併路線で固まり気味。交渉が前に進まんと見るや、ホリエモンは一気にピボット。今度は「買収が詰まるなら新規参入でいく」と方針を切り替え、本拠地=仙台、球団名=仙台ライブドアフェニックス構想まで一気に開示した。ここで大事なんは、承認前から名称・本拠地・体制の“既成事実”を積むこと。意思決定者の脳内に“候補としての具体像”を焼き付けにいってる。
そこへ後追いで楽天も参入を表明。審査は“ネット企業の一騎打ち”に。結果はご存じのとおり11月2日に楽天が採択。でも評価すべきは勝敗やなく速度と代替ルート提示力や。最初の解(買収)が滞った瞬間、第二の解(創設)を世に出して議題を1段引き上げた。これが“ホリエ式の行動設計”——意思決定の遅延を、公開と既成事実化で押し切るやり方やね。
ラジオ局で“奇襲”。ニッポン放送の筆頭株主に一気呵成
2005年2月8日早朝、ライブドアはToSTNeT-1(立会外取引)でニッポン放送株を一気に買い集め、約35%を確保。市場が目をこすってる間に“既成事実”を置きにいったんや。後年の資料でも、オフアワーでのブロック取引が決定打やったことが確認できる。この瞬間、議題は「外部株主が来るか?」やなく「もう来てる。どう扱う?」に切り替わったわけや。
当然、フジテレビはTOB(公開買付)で迎撃。ニッポン放送(NBS)はフジ向けの新株(または新株予約権)発行で希薄化を試みる防衛策を打とうとする。ここでホリエモン側は裁判所という土俵を最短で押さえ、2月下旬に差止め仮処分を申請→3月11日に東京地裁が差止め決定。高裁への不服申立ても退けられ、「経営支配維持のための大量発行はアウト寄り」という判断が社会に刻まれた。スピードで作られた既成事実に、さらに法的な“時間稼ぎ不能”を重ねる。これぞ“制度理解×速度”の合わせ技や。
最終局面は資本取引の大転回。5月23–24日にかけてライブドア系ファンドが保有していたNBS株をフジに譲渡し、フジの持分は約68.9%へ。数字上はライブドアが退くかたちやけど、ネット企業が老舗メディアの支配権争いに本気で殴り込めることを日本の資本市場に見せたインパクトはでかい。「議題を作る側」に回るには、先に既成事実を積んで相手に“事後対応”を強いる——その教科書的ケースになったんや。
逆風でも停止せえへん。逮捕・収監→出所で即“次の打席”
逆風? 関係あらへん。ホリエモンは“止まらん”ことに価値を置くタイプや。2011年に最高裁で実刑が確定しても(=事実としての「失点」)、メンタルは無傷。むしろ「次の打席にどうつなげるか」を逆算しはじめとるねん。
まず獄中でもアウトプットを止めへん。「環境が悪い=発信を諦める」じゃなく、「環境に合わせてフォーマットを変える」。その結果が『刑務所なう。』。制約だらけでも“行動のログ”を取り続け、可視化して世の中に還元。これは“反省の物語”やなく、“行動継続のプロトコル化”や。
出所当日も、じっとはしてへん。2013年3月27日、仮釈放→その日の夜にネット主催の会見へ即登壇。ナラティブ(自分の物語)を他人に握らせず、自分の言葉とスピードで取り返す。ここが“止まらん型の経営者”の肝やねん。
さらに同年、『ゼロ――なにもない自分に小さなイチを足していく』を刊行。「まず1を足す」「小さく速く回す」を一般化して、読者の行動単位に落とし直した。メッセージを“本”というプロダクトに即変換→レバレッジ拡大。
そしてコミュニティは“待たへん”。翌年にはオンラインサロン「堀江貴文イノベーション大学校(HIU)」をローンチ。初期から期制を敷いて、定例会・分科会で“打席数”を仕組み化。個の行動を集合知に変換して、次の実戦機会へブリッジする――ここまで一気通貫。
ロケットは連敗からの宇宙到達。MOMO-3でカーマンライン超え
ここは「行動回数 × 改善速度」がそのまま成果に化けた代表シーンや。
2017年のMOMO初号機は到達前に通信喪失、2018年のMOMO-2は離陸数秒で推力喪失→墜落・炎上。普通は心折れるやろ? でも彼らは“事故報告→原因の因数分解→設計改修→次回計画”を即ループ。負けを“データ”に変換して、行動を止めへんかったんや。
そんで2019年5月4日 05:45(JST)、MOMO-3(宇宙品質にシフト)が打上げ240秒で高度113.4 km、カーマンライン(100 km)を余裕で突破。飛行時間515秒、国内で民間企業単独開発のロケットが宇宙到達は初という区切りも刻んだ。これは“天才の一撃”やない。失敗→改修→再挑戦の回転数の勝利や。
ペンギン先輩的に分解すると、ホリエモン流はこうや——「遅延は最大のリスク。だから失敗の翌日に次の打席を設計」。不具合は“誰のミスか”より“再現条件と対策のリードタイム”で語る。広報も“言い訳”やなく「次はこう直す」の宣言を前に出す。これで支援者の心拍を保ち、行動資源(人・金・時間)を切らさず回すんよ。背景にはタキに常設の射点・常設チーム・スポンサー巻き込みの仕組み化。つまり行動の場を常時温め続ける設計がある。
行動の“仕組み化”。オンラインサロンHIUで動きを増幅
ここは“個人の行動を“仕組み”で何倍にも増幅する話や。
ホリエモンはSNSの発信だけやなく、HIU(堀江貴文イノベーション大学校)という装置をつくって、打席数を常時大量発生させとる。オンラインはFacebookグループ中心、30超の分科会と毎月2回の定例イベント+不定期勉強会で“やりたい”を行動タスクに変換。地方会場とオンライン中継で距離コストもゼロ寄せ。これ全部、動く前提の設計やねん。 堀江貴文イノベーション大学校
運用は期制オンボーディングで回す。毎月「◯◯期メンバー募集中」と期を刻んで入会→分科会合流→即活動のフロー。初手から“どの分科会に入るか”を選ばせて、意思決定の摩擦を最小化する。入会→FB承認(翌月1日開始)→分科会参加申請→活動スタート――この定型導線が“考える前に動く”を支えるんや。
規模感もポイントや。2014年発足後、2019年時点で約1,300名、2022年時点で約900名と時期で変動しつつも、常に数百~千人規模の“行動母集団”をキープ。人数が多いほど小さな挑戦の打席が毎日どこかで立ち上がる。つまり“行動の常温稼働”。
「行動を人任せにせず、行動が勝手に起きる機構を作る」。HIUは、ホリエモンの行動主義を個人→コミュニティ→恒常装置へ拡張したモデルケースや。
行動原則5か条
- 打席至上主義:資料よりアクション。迷ったら“今日やる版”を世に出す。
- スピードは意思:決める期日を今日に寄せる。デッドラインは短いほど良い。
- 可視化=検証:発信は“世の中の反応を集める実験”。数字で次手を決める。
- 逆風活用:批判→注目→説明の導線で、話題を成果に転換。
- 仕組み化:人・時間・ルールを型に入れて、行動の再現性を上げる。
まとめ:考えるより打つ。打って学ぶ。学んでまた打つ。
近鉄買収に手を挙げ、ニッポン放送で議題を奪い、逆風からロケットで宇宙へ。ホリエモンの本体は“動き続けるアルゴリズム”や。
今日のやることリストに、「1件、無茶な打診」を追加してみ。返事ゼロでもノーダメ。1件返ってきたら、世界線が1個ズレるで。ほなまた次回の「経営者列伝」で。
